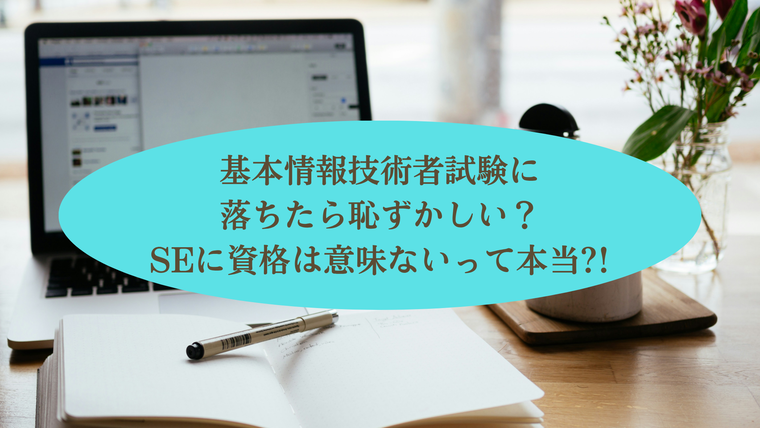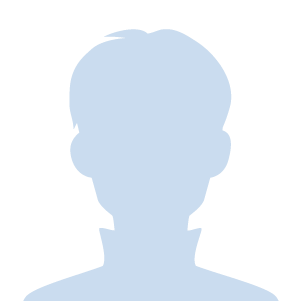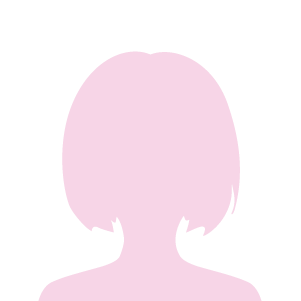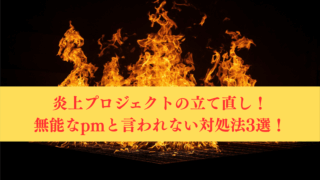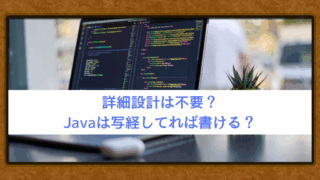目次
基本情報に合格したい!
未経験者のままで本当にIT企業に入っていいのか不安なあなた、勉強はしておきたいけど大学最後の1年なので仕事への勉強に多くの時間を費やしたくはないですし、せっかく受験するなら不合格にはなりたくないですよね?
以下の3つのポイントを押さえれば、合わせてたった1か月・100時間程度の勉強で基本情報技術者試験に合格できてしまうんです!
そのポイントとは…
①科目AとBの得意・不得意を見極めよ!
②午前免除試験を絶対受けろ!
③手書きで処理を追え!
実は、この方法を使って私自身が就職直前の1月に1週間、就職後の4月に2週間勉強しただけで、未経験者で文系の同期の中で、だれよりも早く基本情報技術者試験に合格できたんです!
未経験者の資格試験対策について

それでは、さっそく先ほど紹介した3つのポイントについて、説明したいと思います。
科目AとBの得意・不得意を見極めよ!
基本情報技術者試験というのは、科目AとBの2つがあり、この2つに合格することで得られる資格です。
基本情報技術者試験の概要は以下です。
・科目A
| 試験時間 | 90分 |
|---|---|
| 試験形式 | 選択問題、選択肢は全部4択 |
| 問題数/得点 | 60問/1000点満点 |
| 合格点 | 600点 |
| 試験内容 | ITに関する知識全般 |
・科目B
| 試験時間 | 100分 |
|---|---|
| 試験形式 | 選択問題、選択肢はばらばら |
| 問題数/得点 | 20問/1000点満点 |
| 合格点 | 600点 |
| 試験内容 | 簡単なプログラミングの問題+情報セキュリティについて |
・基本的には科目AとBは同日受験
・不合格の場合、科目Aのみ、科目Bのみの合格であっても、次回は科目AとB両方を受験する必要がある
詳細な説明は以下のホームページなどをご覧ください↓↓
基本情報技術者試験(FE) (受験者専用サイト)
見ていただいたように、試験の内容が全然違うんですよね…
そのため、まず最初にすべきなのが、
「どちらの試験の方が自分にとって難しい・より対策が必要か」
を把握することです。
以下の特徴でだいたい得意・不得意がわかると思いますので、ぜひ参考にしてください。
科目Aが得意なタイプ
・暗記が得意
・歴史や英単語が好き
・問題を解くのが速い
科目Bが得意なタイプ
・考えるのが好き
・数学や古文が好き
・じっくり解きたい
もし、時間に余裕があるのであれば、1回実際の試験を解いてみるのもいいかもしれません。
問題との相性がいいなとか、なんとなくこっちを優先したいなとか、拒否反応があるなとか、いろいろわかると思います!
そのうえで、不得意だ・やりにくいと思った科目への勉強時間を多めにとるようしましょう。
記事の最初に、「1か月・100時間程度」という目安を話しましたが、苦手な科目に6,7割の比重を置くぐらいのイメージを持ってください。
私の場合は、科目Aに2~3週間で70時間、科目Bに1.5週間で30時間程度の勉強時間でした。
順番についても特に指定はないです。科目の内容が全然違うので、どちらから勉強しても不自由しません。
ただし、次の項目で説明するように、勉強する順番のおすすめは「科目A→科目B」です。
午前免除試験を絶対受けろ!
「午前免除試験」というのは、少し前の言い方で、今では「科目A試験免除制度」といいます。
読んで字のごとくで、この制度を利用し合格すると、1年間科目Aを受けなくてよくなります。
制度を使用するために必要なのは、
・指定講座の受講
・「午前免除試験」への合格
の2つです。
詳しくはこちらをご覧ください↓↓
科目A試験免除制度について
この制度を利用することの利点は以下の2つです。
②科目Bの勉強が別にできる
順に説明していきます。
ほぼ丸暗記でどうにかなる
科目Aは先ほど述べたように、IT知識が中心で、暗記力が試されるような試験です。ただ、中には初見だったり、ひねりがあったりする問題が多く含まれます。
その一方、「午前免除試験」では、ほとんどの問題が午前免除試験の過去問からの流用です。
しかも、その過去問は指定講座の中で出てくる問題ですので、別に参考書を買う必要もありません!
大学受験のように、過去問代に費用をつぎ込まなくて済むのは大きいですよね。
何度も講座の過去問を解き、問題の出し方と答えを覚えてしまえば怖くありません!
科目Bの勉強が別にできる
先ほども述べたように、科目A試験免除制度に合格すると、科目Bのみの受験でよくなります。
しかも1か月や2か月ではなく1年間有効ですので、少し時間を空けての勉強でもOKなんです。
これは助かりますよね!
科目AとBは内容が違うので、覚えることも異なってきます。そのため、科目A免除試験制度を使用しない場合には、同時に2つの勉強を進める必要があります。そのため、歴史を勉強しながら数学も勉強するみたいなことをしなきゃいけないんですよね…
それが科目A試験免除制度で合格してしまえば、科目Bの勉強のみに集中できてしまいます!
これは大きなメリットですよね。先ほど「勉強の順番は科目A→Bがおすすめ」といったのはこれが理由です。
科目Aの勉強を優先し、科目A試験免除制度を利用したうえで、科目Bに腰を据えて勉強する。
私自身もこのやり方で合格できましたし、早く合格した同期はほぼこのやり方でした!
手書きで処理を追え!
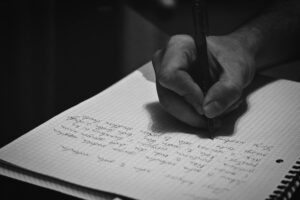
こちらは主に科目Bの勉強方法です。
科目Bの試験では、簡易的なプログラミングの問題が出されます。
プログラミングといっても、JavaやPythonなどの知識が必要なわけではなく、処理の方法などはすべて書いてあります。
そのため、大事なのは「ルールが書いてある処理を読み解くこと」です。
言うなれば、「英単語と構文の使い方が全部出ている英文の和訳」みたいな感じでしょうか。少し気が楽になりましたか?
ですから、勉強の上で大事なのは、「処理の読み解き方」を訓練することです。その上で大切になるのが、紙に処理を書いていくことです。
もちろん、できるようになれば不要ですが、最初は何をやっているかわかんなくなります。そのため、「今は何の処理を書いているんだろう」「何番目まで書いたっけ…?」などを追えるように、紙に文字を起こしておくことが大事です。
処理の内容を覚えるというよりも、書いてある処理を読み取って処理の結果を出すまでの手順に慣れていきましょう。
また、本番の試験でも、使用できるのは紙と鉛筆だけです。パソコン上で、ExcelやWordを使って…ということはできません。
本番の試験に慣れるという意味でも、とても有意義な勉強方法です!
資格に落ちても大丈夫?!
こんな感じで心配している方も多いと思います。会社から絶対取ってくださいと言われている場合を除き、「弁護士の司法試験」「医者の医師免許」などのようにSEに絶対必要な資格というものは存在しないです。
そのため、過度に資格に対してこだわらなくても問題ありません
また、もし基本情報技術者試験に不合格でも、「才能がない」と落ち込む必要はないです!
というのも、IT企業で活躍するために本当に必要な才能は「プログラミング力」ではないんです。プログラミングが不要というわけではないですが、プログラミングの才能なんてせいぜい2,3年目までしか重視されません。
じゃあどんな才能が必要なのかという話はぜひこちらをご覧ください!
文系SEに必要なもの!
文系SEの末路は悲惨?!新卒・IT未経験者でも出世できる!
センスがない!なんて諦めないで!
文系でプログラミングのセンスがない?それでもノーコードはおすすめしない理由!
まとめ
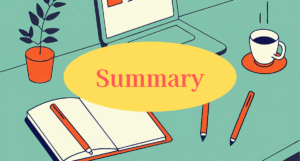
この記事では、基本情報技術者試験への対策を中心に、もし不合格でも絶望する必要はないよということを書いてきました。
実際に、私が働いている会社では、同期の新人が100名程度、その中に未経験者・文系は70人程度いました。彼ら全員が資格を取ったわけではないですし、資格を取っていない友人がSEとして活躍していないというわけでもありません。
資格を取った人は素晴らしい、資格を取っていない人も悲観しなくていい
ということです。
まだSE人生は始まったばかり(というか始まっていないかも…?)ですので、資格に意欲がある方はどんどんチャレンジしてほしいですし、仮に失敗したとしても諦めず再挑戦するのもよし、切り替えて他の能力を磨くもよしです!
あなたのSEとしての活躍を心待ちにしています!
最後まで読んでいただきありがとうございます!